
引用:Google Map
2024年時点で近鉄の駅のうち、1番新しいのは"けいはんな線"の白庭台~学研奈良登美ヶ丘です。
>>木津川台駅は、けいはんな線の1つ前にできた新しい駅だった。新駅設置の理由は?
1994年に開業しました。
その1年前にできたのが、近鉄宮津駅です。
近鉄宮津駅が平成に追加された理由。京都なのに奈良のせい

引用:Google Map
近鉄宮津駅は1993年に新設開業されました。
近鉄京都線では2番目に新しい駅で、近鉄全駅で見ても3位の新しさです。
なぜこんな時期(バブルが崩壊した後)に追加されたのか、その理由を調べてみました。
地元からの要望があった
(現)京田辺市からの要望で、駅を作ってほしいと要望がありました。
理由はハッキリ分かりませんが
そんなに多くの人が住んでいたわけではないので、多分強くは要望してなかったのかも・・・
ですが、近鉄側には駅を設置する理由がありました。
近鉄が新駅を置くメリット

引用:Google Map/KENKENKAICHOさん
近鉄宮津駅ができる前の状態を整理すると
- 新田辺~高の原の間に待避設備が無かった
- 新祝園の待避線は1996年からなので、まだ
- 輸送力アップのネックとなりかねない
この事から待避設備付きの駅ができました。
実はもう1つ理由がありました。
西大寺車庫の縮小をお願いされていた
今でもまぁまぁ大きいですが、過去はもう少し広かった西大寺車庫。
奈良県が整備道路を広くするから、土地を譲れと言ったようです。
この事で車庫のスペースが減ったので、補うために宮津に車庫を置く事になりました。
- 駅設置の要望があった
- 輸送力強化の設備が欲しかった
- 車庫を補う必要があった
この3つが重なって、宮津に新しく駅を設置する事になりました。
近鉄宮津駅の歴史。なぜ冠称が付けられた?

のりば番号に「1」がなかったり、変な所があります。
宮津駅は京都府内にある
宮津駅という駅は、京都の北の方にある宮津市にあります。天橋立がある所。
かってはJR西の駅でしたが、今は京丹後鉄道です。
場所は違いますが、同じ府内で同じ駅名だとややこしいので、「近鉄」と頭に付けるようにしました。
乗り場が2番と3番になってる理由
近鉄宮津駅は、外側に待避線(本線)があるタイプです。
ホームはないけど、外側の線路も1番・4番と数えているため、乗り場は2番と3番になっています。

簡略図ですが、こうなってます。
実際はもうちょっと周辺が複雑ですが、省きました。
近鉄宮津駅と同じように、外側に本線がある駅は布施駅ですね。
同じように大阪線は2と3番ホーム。奈良線は6と7番ホームと、外側線のホームがない分、欠番になってます。
>>布施駅はネタ駅にされるけど、意外とスゴい【2重立体構造駅】
車庫が先にできた
車庫の増備が優先事項だったみたいで、1993年3月18日に宮津車庫ができました。
まだ駅はなく、三山木信号所として開業。
それから半年後の9月21日に駅が完成し、近鉄宮津駅が開業しました。
この年は近鉄宮具駅の開業で、ダイヤが9月にも更新される事になりました。
近鉄宮津駅がある京田辺市南部エリアは酒造が盛んだった

引用:Google Map/YUTAKA OMORIさん
最後に近鉄宮津駅の周辺について適当にご紹介します。
近鉄宮津駅の由来
自治体の名称をさかのぼってみると、近鉄宮津駅の辺りはかつて宮津村でした。
今でも住所として残っていて、シンプルに地名から取っている事が分かりますね。
「宮津」という名称は、基本的にはお宮(神社)に近い港という意味が込められてます。
近鉄宮津駅の近くには佐牙神社や白山神社があり、線路を挟んだ東側には木津川。
地理的に宮津と言われる理由はありますね。
※ただし、合ってるかどうかは別
宮津佐牙垣内
近鉄宮津駅を置くキッカケとなった集落が、宮津佐牙垣内という所。
なんやこれ?と思いますが、分解できます。
奈良県などの関西では、村落そのものを垣内と呼びます。
佐牙神社

引用:Google Map
ほんじゃ佐牙って何や?という話になってきます。
その名前が付いている神社があり、京田辺市のふるさと納税で貰えるお酒の名前にもなってます。
「佐牙」という言葉には酒に関わる言葉です。
現在は酒蔵とかありませんが、かなり昔は酒造りが盛んでした。
どうやら古墳時代よりも前から作られていたようで、良い酒ができますように・・・と神社が建てられたと考えられてます。
ですので、佐牙神社の主祭神はいわゆる古事記などに記されている神様ではなく
佐牙弥豆男神と佐牙弥豆女神が祀られてます。
遠藤川の桜並木

引用:Google Map
京田辺市は2018年度の市長による方針演説で示された散策路の整備で、川沿いの散歩ルートができました。
自然保護と健康増進を目的として、水辺の散策路を複数作りました。
そのうちの1つが近鉄宮津駅の近く「遠藤川 おんごろどん・神楽ルート」です。(赤線がルート)
※スタートは三山木駅
おんごろどんとは、農耕神事の名称。
神楽は白山神社で毎月行われている神楽奉納の事です。
佐牙神社も白山神社も歴史ある古い神社で、重要文化財となってます。
ですが、どちらも小さなお宮で、無人ですので御朱印は貰えません。
まとめ:近鉄宮津駅は様々な事情でできた新駅だった

引用:Google Map
ただ単に地元にお願いされて仕方なく作った駅のようにも見えますが
近鉄側にも事情があったみたいです。
特に西大寺車庫の縮小により、車庫を補う事になったのがデカい理由だったでしょう。
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!
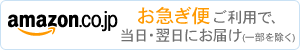
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b74a003.ecacdf55.3b74a004.08d111d7/?me_id=1403058&item_id=10000109&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff262111-kyotanabe%2Fcabinet%2Fd_202203%2F53260111_01_web_s.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

