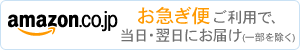引用:Google Map/PONY缶詰さん
ぺーぺー鳴る下りホームの構内踏切
使ってなさそうな引き上げ線
と、駅自体ツッコミ所があり、更に難読駅。
色々とネタがある駅ですね。
今回はそんな弥刀駅についてアレコレ調べてみました。
弥刀駅の歴史。どうしてこんな駅になった?

弥刀駅は普通しか停まりませんが、2面4線の駅です。
ですが駅舎は小さくて、それぞれのホームには別々の出入口があって、構内踏切でしか行けません。

と思いました。
弥刀駅の開業
弥刀駅が開業したのは、1925年12月です。
つまり、弥刀駅は追加駅です。
駅の開業がズレた理由は分かりませんが、優先順位が低かっただけだと思います。
ですので、あとから仕方なく追加した・・・という感じはしませんな。
駅のアップグレードと移転
弥刀駅は最初、2面2線でした。
1949年に2面4線へ増設工事が行われました。
スペースが無かったのか、駅の位置が少しだけ長瀬側に移動しました。
弥刀に待避設備を置いた理由は、ちょうど良い間隔の所だったから。
退避駅の置き方は、3駅に1つあれば輸送力が最大になる(条件付き)ので、弥刀駅が選ばれたのは必然です。
参考論文:列車ダイヤ作成の見地よりする待避線の機能の解析とその計画原則(PDF)

国土地理院地図1936~1942年ごろの航空写真と、現在です。
久宝寺口側の踏切にピタっとあった駅でしたが、今は少し離れてますね。
- スペースが無かったのか長瀬側に移動
- 待避線を外側に増やした
- 駅の出入口どないしよ
そこで駅舎完全別にして、構内踏切を付けた・・・と考えられます。
下りと上りの間に付けなかった理由は、分からん。

とか思ってたのかな?
実は今も使われている弥刀駅の引き上げ線
今は、夜に信貴線の車両交換に使用されているようです。
まず配線略図を見てみましょう。

これだけ見れば、下り線から上り線へ行けそうな感じがしますが、実は渡れません。
弥刀第2踏切のストリートビューで見てみましょう。

引用:Google Map
このように、上り線からは引き上げ線にしか行けないようになってます。
本来は下りから車両を引きあげて上りに送るための設備なので、高安車庫からやってきた交換の車両は

このように動きます。3回方向転換するので面倒くさそうですけどね。
高安から逆走するよりはマシなのかも・・・?
構内踏切、なんであんな音が出るの?
やる気のない音・・・
これは現在、更新されてます。
ワイは電気工学とか全然専門じゃないんで、分かりませんが
音が出る機構が故障してたか、電気系統が少しおかしくなってたと思います。
ぺーぺー音は旧式で、ブーブーは新式らしい。
ですので、更新っちゃ更新ですが・・・なんで音の出だしが、あんな事になってたんでしょうね。
「弥刀」の由来は神社だった。大和川で栄え、大和川に悩まされた地域

引用:Google Map
弥刀駅と同じ名前の神社「弥刀神社」が長瀬駅との間にあります。
正確には彌刀神社。
彌は弥の旧字です。
彌刀神社

引用:Google Map
イザナギとイザナミの間に産まれた男女一対の神で、2柱を総称して
弥刀あたりは昔、大和川流域でした。
約2000年~1800年前くらいは大阪市の大半がまだなく、大阪湾と繋がってたそうです。

引用:柏原市・大和川の歴史
こういった地形から、水戸(港)や河口の神が置かれたのでしょう。
そして「
近江堂エリアの歴史
大和川のおかげで、水も栄養も豊富な土地でした。
ですので農作が盛んでした。
しかし大和川は頻繁に洪水を起こしてて、農地を何度も台無しにしてました。
江戸時代に大和川の付け替え工事が行われ、近江堂あたりもかなり広くなり、集落が増えます。
明治になり、近江堂村と友井村(弥刀駅のあたり)と小若江村(近大のあたり)が合併。
自治体名を弥刀村としました。
「弥刀」にした理由も、よー分かりませんが
- 弥刀神社がある
- 近江堂の由来が大水戸
というポイントがあって、弥刀に決めたのかもね。
弥刀村は1889年~1937年までありました。
その後は布施市になってます。
つーわけで、弥刀村があった所に駅を作ったから弥刀駅に。
弥刀駅は高架化事業が審議中。実現なるか?

弥刀駅は2面4線の駅なんですが、いかんせん不便な構造です。
橋上駅舎とか地下駅舎がなく、それぞれ別。
構内踏切があっても、上下ホームの行き来ができません。

と思ったら、東大阪市議会で高架化の話がありました。
住民からの要望もあり、高架化するかも
踏切では何度か危険なシーンがあったようで、安全性の事なども含めて「高架化してほしい」という声が上がってました。
ですが、議会での話はまともに進んでません。
というのも隣の八尾市との話、予算の計上がまだできてないので、状況としてはゼロ地点。※2024年3月末時点
実現はかなり難しいでしょう。
この事からも、まだまだしばらくは面倒くさい駅構造のままになりそうです。
参考:東大阪市議会会議録の検索
請願自体はまだ生きているようですので、東大阪市議会の建設水道委員会のやる気次第かも?
弥刀駅に千日前線はくる?
千日前線の延伸計画として、南巽駅から東へ延伸して弥刀駅を通る・・・
なんて計画がありましたが
完全に話が消えちゃってますね。
- 費用対効果が見込めない
- おおさか東線の旅客運送が行われている
という理由から、千日前線が弥刀まで延びてくる事は、ほぼ無いでしょう。
そもそも弥刀から千日前線を通って難波まで行く人居るの?近鉄があるのに
運賃面では不利ですが、速達性は近鉄だと思います。
まとめ:弥刀駅で特急回送の退避は見れる?

引用:Google Map
過去には"しまかぜ"が高安→難波への回送中に停まってたらしいですけど
今は、どうなってるんでしょうね。
さて、弥刀駅の周囲はそんなに紹介する所が無いので今回は省きました。
適当に評判を見てみると、住民はそこまで不満のある所ではないみたい。
学校も近いし交通も悪くないし、治安も悪くないし、生活必需品の買いだしにも困らないし。
駅からほど近い金岡公園は野球場、テニスコートもあり、春は梅と桜が見れるようです。
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!