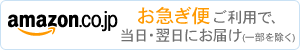引用:Google Map
管理人のワイ、大阪だもんで名古屋線の駅を全然やってねーな・・・
というわけで、適当に名古屋線の駅で気になる駅を選びました。
この辺りが気になったので、毎度のごとく適当に調べてみました。
伊勢若松駅の歴史。最初から分岐駅の候補だった?

伊勢若松駅の開業は1917年12月22日です。
今で言う近鉄名古屋線が津~千代崎まで開通した後にできました。
千代崎~楠まで開業した時に、若松も開業しました。
伊勢若松駅の駅名は・・・
駅名の由来は、海岸にある松並木です。
よく「吾の松原」と混同しますが、ちょっと違うらしい。
「吾の松原」は、万葉集の歌にあります。
「妹(いも)に恋ひ 吾(あが)の松原 みわたせば 潮干(しおひ)の潟に 鶴(たづ)鳴き渡る」(万葉集1030番目の歌)
で、伊勢若松あたりの松原は、別の歌でチラホラ詠まれてたらしい。
鈴鹿市若松地区の松原は、海のそばまで行けば名残がありますね。
千代崎の方まで南下すると、結構残ってます。
海の近くでは海水などによる塩害や、砂の影響を受けてしまいます。
そんな環境では普通の植物が枯れてしまいますが、松は平気。
ですので、防風林のような役目として松が植えられる事になりました。
鈴鹿線を作った理由
なぜ名古屋線を作った伊勢電は、直で鈴鹿市の中心部に繋げなかったのか。
それは、津と四日市を最短距離で結びつつ、海に近い町の利便性を考えたから。

と、最初から考えてたと思います。
あまり内陸に作ると、国鉄とバトってしまいますからね。
鉄道の免許も通りづらいです。
鈴鹿線の歴史はこちら→近鉄鈴鹿線はなぜできた?伊勢電の戦略が垣間見えた
なぜ若松を分岐駅に設定したのか。鈴鹿線のルート設定は
その理由は、地形と集落の位置にあると考えます。
- 金沢川
- 柳駅周辺のエリア
千代崎と若松の間には金沢川があり、柳駅周辺の集落は若松側。
以上の理由から、若松から分岐させる方が建設がラクという判断でしょう。

そして若松と鈴鹿市駅の間です。
この間には古くから道路があったようで、古い神社もあります。
土師神社と西土師神社は江戸時代からあるらしい。
参考:神社検索(三重)
で、この地域より北側は農地。
というわけで若松から分岐させ、四日市側から入るルートに設定したと考えられます。
そもそも若松地区はどんな地域なのか
鈴鹿市の若松地区は、漁業が盛んな地域です。
今は若松漁港として残ってますね。
そこで獲れた魚を、城下町の神戸地区(鈴鹿市の中心街)に運んでたのでしょう。
そのための道路に沿って鈴鹿線を作った、と考えられます。
ちなみに鈴鹿市の3大地区は神戸・白子・牧田で、鈴鹿神戸は鈴鹿市駅。
白子駅についてはこちら→なぜ白子に?伊勢若松を差し置いて特急停車駅になった理由
若松漁港の防波堤あたりでは、アジやメバル、キスやチヌといった美味そうな魚が釣れるらしいです。
参考:若松漁港の釣り場情報
伊勢若松駅は急行停車駅として、ふさわしいのか

次は伊勢若松駅の最近や将来について、好き勝手に言います。
伊勢若松駅は本線と支線の分岐駅なだけあって、急行停車駅に設定。
でも、そんなに若松で降りるのかというと、そうでもない。
前後の白子や塩浜に比べたら、乗車人員はかなり少ないです。
前後の急行停車駅との差
伊勢若松駅の1日平均乗車人員は、1,135人(2019年)でした。
同年の塩浜と白子は
- 塩浜:3,468人
- 白子:8,366人
白子は鈴鹿市第2の地区で、白子地区です。
塩浜は四日市市の南に位置していて、いわゆる中京工業地帯(四日市)の一部。
石油コンビナートがあり、多くの方が働きに出ているでしょう。
それに比べて若松は1,135人と少なめ。
こんな数値だと、若松は分岐駅だからという理由だけで急行を停めている・・・としか思えませんね。
退避可能駅になった理由は、理論上の話
退避可能の駅は四日市~津で見ると
四日市・塩浜・楠・伊勢若松・白子・豊津上野・白塚・江戸橋です。

ちょっと偏ってる所もありますが、だいたい3駅前後の間隔にあります。
条件によりますが、3駅ごとの待避設備は輸送力を最大化できる一定の基準です。
というわけで若松に待避設備を置くのは、まぁ妥当です。
鈴鹿市の住民の移動需要
2022年12月17日ダイヤで見ると、鈴鹿線と名古屋線の接続は上り(四日市方面)の接続の方が基本的に良いです。
※通勤通学の平日朝ラッシュ7時台を見ました
古いデータですが、昼間は四日市市へ行く人が多くて17,140人。津市が5,454人でした。
参考:鈴鹿市
まぁ鈴鹿市全体でのデータですので、一概には言えませんが・・・
ですが、三重県は車移動をする人が多くて、鈴鹿市もそれは一緒。
JR・近鉄・伊勢鉄すべてを合わせても、自家用車で移動する人の方が多いみたいです。
高校生は電車移動が多いですが、同じくらい徒歩・自転車で通ってる人が居ました。
ですので、一応・・・需要に答えてはいるけど、そこまで利用者が多いって事でもないようです。


なんて声もあったそうです。
参考:鈴鹿市 地域公共交通の利用実態・ニーズの把握、結果概要(PDF)
鈴鹿市への流入も四日市市民が1位。津市民が2位で、この2つはあまり差が開いてませんでした。
なんし車で移動する人が多いため、近鉄はあまり本気で住民の足になろうとは考えてないかもしれません。

駅前の像、誰やねん?

引用:Google Map/Hirotaka Yamamotoさん
伊勢若松駅の出入り口前には、像があります。
「大黒屋光太夫」だいこくや・こうだゆう、という人で江戸時代後期、白子・若松付近で船長をしていた人です。
ただの船長が銅像として置かれる理由はありません。
- 船が漂流し、ロシアに漂着
- ロシア語を学びながら他国の事を知る
- 江戸時代の間に帰国できて、蘭学の発展などに貢献
蘭学と言えば、今で言う医療系の学問という印象がありますが・・・
正確に言うと、ヨーロッパの学問や文化、技術全部ひっくるめて言うそうです。
まとめ:伊勢若松駅は色々と理由があって今に至る

引用:Google Map/Lr 531さん
鈴鹿線のルート設定、なぜ津方向から行けるようにしてないの?
急行停車駅にする必要あんの?ってくらいの閑散した駅。
てか、松が見当たらないけど、なんで若松?
以上の理由を考察してみました。
近鉄が(伊勢電が)適当に作ったんじゃなく、理由は色々とあったようでした。
それでは、今回はこの辺で。またの。
これからも、近鉄駅の歴史や疑問に思った事を適当にご紹介します。
「これやって」「あれ何やろか?」あれば、コメントやTwitterなどに投稿してください。
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!