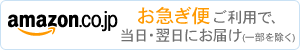なにがネタなのかというと、近鉄の大和西大寺駅から行ける、3か所の「九条駅」の1つだということ。
さて、私はてっきり・・・・
と思ってたら、大和郡山市でした。
なぜ「奈良市なんじゃないの?」と思ったのは
どうやら勝手な想像だったようです。
九条駅(奈良)が大和郡山市である理由

ざっくり解説すると
- 平城京ができた時に西京の9条あたりが今の九条駅
- 平城京から長岡京へ引っ越し
- 平城京の跡地は放置プレイ
- 近場の寺社に力があって、街は維持
- 織田家の時代に発展
- 豊臣家の時代にさらに発展、安定する
- 江戸時代、郡山藩が成立
- 明治、九条村ができて、のちに郡山町となる
- 郡山町は周りと合併して大和郡山市に
こんな感じです。
平城京と橿原線を重ねてみる

引用元:平城京条坊図(PDF)
新大宮駅と奈良駅は描かれてますが、橿原線がなかったので大体の位置に描きました。
ゆうて九条は8条大路のあたりなんですけどね。
この辺り一帯が“九条村”だったのか、九条にしたのかもしれません。
九条大路は、今で言うと「奈良大和郡山斑鳩線」だと思っていいです・・・地元の人しか分からんと思うけど。
宮をホイホイ移動する理由
昔は天皇の家である「宮」をあちこち移してました。
時には橿原市や明日香村。大津市だったこともあれば、今回の奈良市、そして長岡京市に京都市。
かなりの昔は今よりも全然科学や医療が発達してなくて

という理由で、引っ越しを繰り返してました。単純に“1代きり”で宮を変える風習だった事の方が理由として強いですが。
ちなみに流行り病が広がったり、自然災害とかで食べ物が足りなくなった時は、元号を変えることがありました。
今からしたら「なに無駄なことしてんねん」と思うかもしれませんが、当時はよく分からないことが起こったら神様や仏様にお祈りしとけば良くなると信じられてたんですよね。
平城京への引っ越し理由
藤原京では、そこそこうまくいってたのですが
- 衛生状態が悪くなってきた
- 治安のことも考えて離れるべきと判断
- 最新の政治を行うためには、都市構造が最適じゃない
という理由で、平城京への引っ越しを決めました。
平城京から長岡京へ
平城京に引っ越ししてからは、しばらく安定しました。
その代わり、力を持ち始めた人たちは

と争いが増えるし、天然痘っていう世界TOP6のうちの1つのヤバいウィルスが広がったり、仏教ひいきをしすぎたせいでパワーバランスが崩壊。

これで平城京は解体されてしまいます。
当時の寺社は今でいう自衛隊に近い
今では考えられないでしょうが、昔のお寺さんは武力まで持ってて、かなり強いのです。
そのおかげもあって、しばらくは地域の農家を取りまとめて勢力を維持し続けていきます。
戦国時代になっても、大きな影響を受けずに平城京跡の地域は残り続けました。
織田~豊臣の時には平城京跡から郡山城あたりにかけて、産業が発展。
江戸時代には郡山藩が郡山城を中心に政治を行って、しばらく安定しつづけました。
九条村の成立→現代
1889年に九条村は郡山町の一部となります。
郡山町はしばらくの間、名前を変えずに周りの自治体を吸収しながら大きくなり、1954年に大和郡山市に名前を変更します。
確かに1300年前に九条駅の辺りは平城京って都の一部だったんですけど
都が移ってしまって、その後に郡山藩の仲間入りしてしまったせいで、大和郡山市になった・・・ということです。
九条駅ができた時の話

引用:国土地理院地図
1921年に大軌は畝傍線を開業します。
この時に九条駅も含む、周りの駅も同時に開業しました。
駅間の距離を見てみる
- 西大寺~尼ヶ辻:1.6km
- 尼ヶ辻~西ノ京:1.2km
- 西ノ京~九条:1.2km
- 九条~郡山:1.5km
どの駅も、ほどほどの距離感ですね。
- 北側に作ると距離が短すぎる
- ルート設定的に、かすめるのは仕方がない
- 城の横だと駅の敷地確保が大変
というわけで、郡山駅は城の南に。
尼ヶ辻・西ノ京の駅名は
尼ヶ辻は、興福院(こんぶいん)という尼さんのお寺と、三条大路と西一坊大路の大きな道の十字路が近くにあることから。
十字路のことを「辻」と言います。
ちなみに、興福院は移転して現在の場所(奈良市法蓮町)になりました。
西ノ京は、平城京の西京から。
ちょうど西京エリアの真ん中あたりだし、唐招提寺・薬師寺にとても近い場所という立地。
西京の好立地だから、西ノ京となりました。
九条駅は・・・
特に他に採用するものが無かったと考えます・・・(笑)
歴史を振り返っても九条村のあたりだし、九条~八条の辺りだし
ケチのつけようがない、駅名の選び方でしょうね。
大和郡山市は奈良県の中では4位の規模。九条駅あたりは閑静な住宅街ですね。
住みやすいかと言われたら微妙だと思います。
まとめ:歴史が古い方より新しい方を重視する?

九条駅のあたりは、てっきり奈良市ギリギリかと思いきや実は大和郡山市でした。
確かに九条という名前は平城京の名残ですが、あとで郡山藩のエリアになってしまったことで、のちに大和郡山市に。
まぁ、平城京の長さよりは郡山藩のエリアだった時間の方が長かったのもあるのでしょう。
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
X(Twitter)
アカウントをお持ちの方はぜひフォローを。
PIXIV FANBOX
特に良く撮れた写真をアップします。