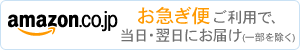さて、今回は「大和八木駅」
大和八木駅は近鉄でもかなり重要な駅で、ほとんどの特急が停まります。
まぁちょくちょくYouTubeでネタになる近鉄の駅の1つだし、撮り鉄にも人気の駅ですね。
ワイは編集とかアレコレ面倒臭いんで、ブログという形ですが大和八木駅の紹介をしていきます。
大和八木駅の今

大和八木駅は西大寺みたいな感じではなく、改札外にチラホラとお店がある感じ。中にもちょっとありますが・・・
近鉄は八木駅をこれ以上、手を加える気が無さそうな感じがします。
運行上はかなり重要な駅なんですけど、駅周辺がしっかりしてる分

と思ってるのかなぁ?
駅直結ではないですが、近鉄百貨店もありますし
橿原店は、東大阪店とは違って地下から7階まであってレストラン街もある、ちゃんとした?百貨店です。
特急の乗り継ぎ

ただし、ひのとりの一部。土休日の大阪難波発着、伊勢志摩ライナーの一部は停まりません。
基本的には橿原線に停車する、京都から来た橿原神宮前行きの特急と名阪特急や阪伊特急との接続が行われます。
一応、京都行きの特急も30分以内に乗り換えが可能です。
もう1つは、大阪から来た名古屋行きの特急と、京都から来た賢島行きの特急。
これは2階ホーム上の対面乗り換えが行われます。
各時間の頭の方では、名阪との乗り換え。40分くらいには賢島行き特急と京橿特急が連絡します。

ちなみに、知ってる人は知ってますが、近鉄は特急を乗り継ぎしても30分以内の乗り継ぎは、通算で計算されます。
まぁ近鉄だと特急の2列車乗り継ぎは、当たり前のようにあります。
大和八木駅で乗り換えるパターンもありますが、伊勢中川で乗りかえる事も。
ちなみに最短ルート設定では4回の乗り換えが可能です。
どうやら謎の条件があれば、5回の乗り換えが可能らしいですが、ちょっとそれは調べきれてません。
また分かったら追記します。コメントで教えて下さると、嬉しいです。
大和八木と八木西口、近すぎん?
よくネタにされるのが、八木西口駅と近すぎる。という話

実際には駅の真ん中くらいで測ると390mくらい離れてるんですが、実は同一駅扱いとなってます。
だけどこの2駅間を電車で乗って移動する場合は、初乗り運賃が必要です。
まぁ入場券と同じ値段なんで、損する事はないです。
なぜ、こうなってるのかというと・・・
こういった経緯から、大和八木=八木西口という扱いになっているのです。
大和八木の楽しみ方(?)
近鉄では布施・八木・西大寺のトライアングル部分は初乗り運賃で大回り乗車できるんで、JRのような楽しみ方もできます。
布施・鶴橋間については特急や快速急行といった、布施に止まらない車両に乗っても、環状経路を認めることになってます。
ちなみに、営業距離が1番短いのは八木・八木西口間を除くと・・・

引用:近鉄営業キロ程表
近鉄が出している営業キロは0.5kmで、よくネタにもされている伊勢市・宇治山田間は0.6kmとなってます。
関連記事:>>近鉄の駅間距離を調べてみた
まぁ、伊勢市・宇治山田間はどっちも特急が停まるっていう事も合わさってネタになるんですよね。
↓↓こんな事も出来ますからね(笑)
これ以上に近いのが八木・八木西口駅です。
どうしてこうなったのか、というと八木西口駅の歴史に理由があります。
撮り鉄に嬉しい駅?

大和八木駅はカーブがある駅ですし、特急のすれ違いがよく見れます。
土休日の夕方限定ですが、しまかぜ+ひのとりのコラボも見れます。時間は17時51分頃
個人的には鶴橋の次によく撮ってる駅です。
大和八木駅の歴史

大和八木駅の場所は最初、なにもなくて今の橿原線だけがありました。
近鉄の主要駅となりました。
八木西口駅が最初
最初は今の八木駅の場所には駅は無く、八木西口の所に「八木駅」がありました。
1923年に八木駅(現在の八木西口)が開業。
のちに八木駅~高田が、後の大阪線になる一部分が開通します。(1925年)
またそっから桜井の方に延ばそうと思った時(1929年)

と決めて、今の大和八木駅に移したんですけど、八木西口駅をそのまま存続させました。
当時はまだ上本町~橿原神宮前の営業設定があったため、八木に電車を停めるためにも駅を残しておきたかった。
で、結局残っちゃった・・・というワケです。
後になって駅なくしまーす。ってするのも色々と面倒らしいです、よー知らんけど
近鉄路線の開業年月日まとめ記事はこちら→近鉄はどうやってできた?歴史をイチからたどってみた(前編)
八木西口短絡線の今
昔は営業列車が通ってたようですが、今は整備するための電車がたまーに通るくらいです。
というのも、近鉄は電車の整備のほとんどを五位堂で行うようになったので、南大阪線や吉野線で使っている電車を五位堂に送るために西口短絡線を使うしかないんですね。
ちなみに、イベントで営業列車や貸し切り列車を通す事もあります。
貴重な前面展望を撮影して下さってる人が居たので、紹介しときますね。
新ノ口連絡線
さらに後になって追加されたのは新ノ口連絡線です。
これが出来るまではスイッチバックを2回やって、橿原線と大阪線の直通を行ってました。
今の西口短絡線を使ってた、という事です。
こんな事、近鉄がほったらかしにするワケがなく、1967年に新ノ口連絡線を完成させました。
ちなみに伊勢中川短絡線は1961年に完成しています。後に更新されましたが。
で、ちょくちょく「新ノ口短絡線」と言う方が居ますが、「新ノ口連絡線」なんですよね。
何がどう違うんか、というと
短絡線は、連絡線という種類の一部
短絡線は、2つの路線をなるべく短い距離で結んだ線路の事
新ノ口連絡線は、高田側でぐるっと回るんで、短絡線と言うにはちょっと違いまっせ。と言う事。

大和八木駅の周りは
歴史的には八木西口駅の方が長いんで、橿原市役所は西口の方が近いです。もう、下りてスグです。
でも大和八木駅からも歩いて行ける距離ですけどね。
他には文化会館。1300人収容できる大きなホールがありますね。
ただ、庶民の味方?イオンモールは万葉まほろば線の金橋駅が最寄。
ですがさすが田舎というか、ちょっと都市部から離れてるというか、駐車場は広くて無料なんですよね。
ちょっとでも都市部から離れたら、もう車が無いと生活できませんから
駐車料金取ってるようじゃ、お客さん寄り付きませんよね
で、地理院の地図ですが、昔の航空写真は無かったんでどうにもこうにも分かりませんでした。
あったのは1960年代の航空写真からで、

やっぱり先に出来ていた、今でいう八木西口の辺りは栄えてますね。
だんだんと大和八木駅の北側に住宅や、なんやかんやと出来てきたって感じでした。
まとめ:大和八木駅は珍しい同鉄道会社の立体交差駅
大和八木駅はいかがでしたでしょうか。
私の生活圏内からだと、ちょっと距離があって鶴橋駅でお腹いっぱいになっちゃうんで、わざわざ八木まで駅撮りはしに行かないんですけど
なかなか面白い駅です。ホーム長も結構あるんで、端っこで撮る写真は結構ええ感じですよね。


反対の耳成側は、ホーム方向を撮るのが良いですね。


動画は2つあるので、ぜひご覧ください。
土休日限定。伊勢志摩ライナー甲特急の通過と、新ノ口連絡線の前面展望(伊勢志摩ライナー)をどうぞ
他にもSNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!