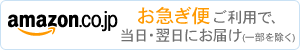引用:Google Map

どういうこった?と思って、適当に調べてみました。
また、いつものように今里駅の歴史や駅周辺の事を紹介します。
- 近鉄と大阪メトロの今里駅が離れている理由
- 2度の駅名変更があった、今里駅
- 今里駅に人が集まる可能性アリ・・・しかし
近鉄と大阪メトロの今里駅が離れている理由

近鉄の今里駅と、大阪メトロの今里駅は750mほど離れてます。
当たり前ですが、こんな距離なので乗り換え案内はありません。
この2駅の歴史を辿ると、どうしてこうなったのかが分かります。
近鉄奈良線が開業する
先にできたのは近鉄奈良線。
1914年4月30日に大阪上本町~近鉄奈良が開通・開業しました。
同じ日に今里駅(当時は片江駅)が開業。
千日前線はかなり後で1969年に部分開業しました。

引用:東成区
片江というのは、大阪市東成区の今里駅あたりの事を指します。
住所としては残ってなくて、かつて呼ばれていた地名です。
1度目の駅名変更「今里方江」に
開業から8年後の1922年、駅名が「今里方江」になりました。
理由はよく分かりませんが、今里が付きました。
今里という地域名は、さっきのように東成区の真ん中の事を指すんですが

東成区から生野区にまたがった赤線の範囲内の事も、今里と言います。
今里片江→今里に変更
1929年、今里駅に変更しました。
コレもハッキリとした理由は、よー分かりません。
時期的には今里の区画整理事業が行われた時と同じでした。
多分、この町づくりに合わせて今里にしたんでしょう。
で、「今里」という地域について調べてみた所・・・
その村が大今里・西今里・東今里などでした。
こいつらの範囲が、さっきの赤線の範囲。
ちなみに「カタエ」という名前の方が由来的には古いと言われてます。
河川が交わる江が今里駅のあたりだったそうで、「交江」と言われてました。
参考:生野区
大阪市営地下鉄が東西線を計画

引用:Google Map
中央線は計画どおりだったんですが、それだけじゃ足らんという見通しになり、千日前線も追加することになりました。
そして大阪市は路線計画を立てます。
過去には野田阪神~神崎川や南巽~国鉄平野と伸ばすプランがありました。
ま、実現はしませんでしたが。
交通局の財政的な事情が主な理由です。
大阪メトロ今里駅が今里交差点に選ばれた理由は
近鉄今里と大トロ今里が離れている理由をまとめると・・・
ということ。
つまり、新しい今里って町ができたから今里駅にしよう。
という単純な話。まだ千日前線ができてなかったんで、「新今里」と付ける必要がなかったのです。
大阪メトロ側は、他に適当な駅名が無かったから同じにしたんでしょうな。
しかも当時は大阪市交通局です。
冠称などを付ける事は考えても無かったんでしょう。
今里駅の歴史。2面2線で支えていた中間駅

今里駅は3面4線ですが、最初は2面2線でした。
複々線化が完了したのが1956年でした。
それまでの32年間は、2面2線で奈良線と大阪線をさばいてました。
軽くおさらい
今里駅は1914年4月30日に開業しました。
当時の駅名は片江駅でした。
1922年に今里片江駅に変更。
これについては「近鉄100年のあゆみ」に記載があったのですが、どこぞの別著書で一部否定する記述があったらしい。
今里駅のあたりは区画整理される事になり、新たに新今里という町ができました。
これを機に駅名を今里駅に変更しました。
近鉄大阪線の開通

最初は八尾まで。
翌年の1925年には恩智まで繋がりました。
この時はまだ今里駅に大阪線の車両は停まってたと考えられます。
1929年、大阪線は厳しい山越えのために1500V仕様に変更します。
ですが布施から上本町は600Vのまま。
このため、大阪線の車両は今里駅を通過する事になりました。
- 電気不足のため速度がでない
- 同一線路を使うため、キャパオーバーに
- 大阪線は通過して少しでも流すようにした
そんな期間が少なくとも32年間あったようです。
途中、複線の状態での高架化工事がありました。
複々線化の工事が行われた
1956年12月8日、布施~鶴橋の複々線化工事が完了しました。
この時、今里駅に新しいホームが新設されます。
今の4番のりばホーム(大阪線上り)が追加されました。
当初の運用は、こうなってました。

まだこの時代は、全てが大阪上本町駅から出ていたので、特に問題はありません。
今度は近鉄難波線の開業です。
1970年3月15日、難波線が開業して具合が悪くなります。
大阪線利用者が難波まで行く時に難儀です。
- 布施で奈良線を待つか
- 今里、鶴橋、上本町で別ホームへ移動するか
この不便を解消するためでもあったのが、方向別複々線への切り替えです。

1975年9月14日から、この運用に変わりました。
13日の深夜から14日かけて、大規模な切替工事が行われたそうです。
今里駅はこれから撮り鉄スポットになる?

今里駅の周辺は特にコレというものはなく、住宅街です。
しかもターミナル駅に挟まれているせいで普通しか停まりません。
ですので、ちょいと利用者は少なめ。
鶴橋駅の工事で、今里駅に人が集まる可能性あり
鶴橋駅はホーム柵を付ける工事が始まりました。
全て完成した場合は、駅の端っこでの撮影が困難になるんじゃないかと言われてます。
そのため、今里駅にカメラ野郎が移動する可能性アリ。
今里もよく撮影されている所ですが、更に多くなるかもしれませんね。
熊野大神宮

引用:Google Map
近鉄の今里駅からは少々歩きますが、この辺りでは1番大きな神社。
名前の通り、熊野本宮の分社です。
伊勢は行きやすいですが、熊野は結構大変ですからね。わりとオススメかも
料亭?が並ぶ今里

引用:Google Map
今里には風情ある料亭が数軒あります。
規模的には大阪で1番小さいです。
受付に居るお姉さま(?)に好みの女性の外見を伝えましょう。
キレイ系が良いのか、可愛い系が良いのか・・・
そしたら、どっからか女の子がやってきます。
料亭の部屋に入り、女の子と二人きりの食事をお楽しみください。(知らん顔)
高架駅なのに改札口は1つ
面倒くさいことに、今里駅は南からしか入れない構造となってます。
ですが高架駅という構造を活かし、連絡通路は確保されてました。
布施側は駐輪場に。鶴橋側は高架下を通る道があります。
今以上に良くして欲しい・・・という要望は挙がってないそうで、しばらくは改良工事などが無さそうでした。
まとめ:今里駅は2回変身していた。そして衰退へ?

フリーザ様?
今里駅に改称した時、駅周辺は結構賑わってたんですよマジで。
ただ1950年台に大人の事情があり、少しずつ衰退。
今では、ほぼただの住宅地です。
鶴橋駅のホーム柵設置により、撮り鉄どもが今里に移動するかも・・・?
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!