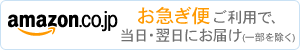引用:Google Map
- 全線単線
- 駅数は3駅
- 使用編成が1編成のみ
- 少ない時は1時間に2往復
と、かなりローカルっぽい路線ですが、実は結構重要な路線でもあり、近鉄では最古の路線です。
今回は、そんな陰が薄いようで重要な路線、道明寺線の歴史などなどを取り上げます。
近鉄道明寺線の歴史

引用:Google Map
2番目は長野線。
ですが、当時は近鉄系列とは全く関係のない会社が作りました。
バイパス路線の計画
道明寺線は「河陽鉄道」が作りました。
それ以前に、今でいう大和路線も完成していて、南海高野線も河内長野~堺東が開業済。
道明寺線と長野線の誕生で、便利なバイパス路線が完成しました。
ですが、本来は観心寺や高野山にまで延伸するつもりだったようです。
経営破綻した河陽鉄道
1898年3月24日に柏原~古市が開業しました。
ですが、その翌年に経営破綻してしまったので、経営を「河南鉄道」に引き継がせました。
そうして、とりあえず計画通りに河内長野まで延伸。
道明寺線と長野線が完成し、目的は達成しました。その先の延伸計画もありましたが、実現はしませんでした。
関連記事:近鉄長野線の歴史を掘り起こすと、近鉄イズムが隠されてた?
大和橋駅の開業
1911年11月12日に柏原と道明寺の間に新駅が開業しました。
当時は大和橋駅で、今の柏原南口駅よりも600mほど南にあったみたいです。

引用元:国土地理院地図
大和川の対岸にあったそうですが、数字と場所が何となく合ってない気がするので、600mは間違いかもしれません。
対岸なら300mですね。
ちょうど民家がありますし。
大和橋駅は、1924年6月1日の電化と同時に移転。柏原南口駅に改めました。
ですが、この情報も確定ではないそうで、大和橋駅を廃止して新しく作った、とも言われてます。

河南鉄道と国鉄の間で起こったイザコザ?
河南鉄道が持っていた、今でいう道明寺線・南大阪線の一部・長野線は南大阪の良いバイパス路線で、一応順調だったようです。
昔は今のJR難波駅から道明寺駅まで、直通列車があったくらい。
しかし、国鉄の良いように使われるのが気に入らなくなったのか、自社で大阪市への乗り入れを目指しました。
そうして河南鉄道は大阪鉄道に社名を改めて、大阪市への乗り入れを実現させます。
これが後の南大阪線となるわけです。


引用:wiki大阪鉄道・路線図
道明寺線が支線へ降格
大阪鉄道の方針により、道明寺から大阪阿部野橋へ新たに延伸。
1923年4月に完成しました。
1929年3月には古市~橿原神宮前が開業して、道明寺線は完全に支線へ降格。
この頃の大阪鉄道は、バッチバチに近鉄(大軌)とバトルしていて、吉野線を取れるかどうかで負けたし、4月には衝突事故(上ノ太子)が発生。
なかなか大変な年でした。
10月の大阪鉄道の株主総会では、金森や種田(大軌の重役)が大阪鉄道の取締役に就任する議決が通ってしまいます。
近鉄の社長なのに、別の鉄道会社の社長も兼任したような感じ。
これで実質、大軌のモノとなってしまいました。
こっから先は、例の合併物語です。
その辺の詳しい話は↓
>>近鉄はどうやってできた?歴史をイチからたどってみた(後編)をご覧ください。
順番に近鉄の歴史を辿っていってるので、分かりやすいかと思います。
近鉄道明寺線の今

引用:Google Map
いつの間にか支線にされてしまい、今は柏原と道明寺を行ったり来たり。
1編成の電車がピストン運行してます。
車両の検査などのために道明寺駅には渡り線がありますが、南大阪線に直接入る定期列車はありません。
実は利用者が結構多い
2018年11月13日の特定日調査で、柏原駅の1日乗降人員は6,469人でした。
この数字はまぁまぁ多く、特急が停まる尺土よりも多いです。
とはいえ、利用者の多くは通勤通学のために利用していると考えられます。
実際使っているかどうかは置いといて
この事が柏原市統計書2022年版から分かりました。
つまり、単線で1編成しか動いてない、一見ローカルっぽい路線でも、かなり重宝している路線だという事が分かります。
そのため、ラッシュ時間帯は1時間に4往復も運行。
人様の足として機能してます。
まぁまぁ便利な同一ホーム

柏原駅のホーム上にはICカードをタッチする機械が置いてあり、これにタッチすることで改札を出なくてもJRに乗れます。
このおかげで関西近郊は、頭がおかしいノーラッチルートが構成できるようになってます。
全てが自由に乗り継ぎできるわけではありませんが、理論上は可能です。
近鉄は大阪メトロ、京都市営地下鉄、JR東海と改札内乗り換えが一応できます。
ちなみに近鉄とJR東海とは改札内で乗り換えようと思えばできますが、エラーが起こったり、不正乗車になるので、やめましょう。
さて、脱線はこの辺にして・・・
柏原駅は物理的に出てないだけで、ICカードのタッチは必要です。
ただ、道明寺線とJR大和路線との接続は全く考慮されてないので、そんなに接続は良くありません。
柏原駅は普通しか停まらんし。
大阪線との徒歩乗り換えOK
定期券に限りますが、道明寺線の柏原駅と柏原南口駅は、大阪線の駅と乗り継ぎができます。
どっちのが便利かどうかは・・・微妙ですね。
どっちの駅も区間準急までの種別が停まるので、料金や時間で決めたら良いんじゃね?と思います。
1軒の家にしか繋がってない踏切

引用:Google Map
道明寺線には踏切が4カ所ありますが、そのうち1つは1軒の家にしか繋がってない踏切があります。
この踏切は勝手に作った踏切とかじゃなく、ちゃんとした踏切で、第1種踏切です。
第1種踏切ってのは、装置が全部付いている全自動踏切のこと。
全国の踏切のほとんどが、この第1種踏切です。
近鉄で、こんな踏切は1箇所くらい。
大阪には同じような踏切が、阪急宝塚線にもあります。(豊中市刀根山3丁目1あたり)
まとめ:近鉄道明寺線は降格されても頑張ってる

引用元:Google Map/Yoshihiro Makinoさん
近鉄道明寺線は、近鉄が今持っている路線の中では1番古い鉄道路線です。
全線開業という基準で言えば道明寺線が最も古くて、次点が長野線。その次が湯の山線です。
ただ、柏原南口駅は最古の駅ではありません。
柏原・道明寺・古市が近鉄の駅の中で最も古い駅です。
古市駅についてはこちら→近鉄、最古参の駅の1つ『古市駅』で見られるKTクオリティとは
今や1編成だけで往復するローカルっぽい路線ですが、ラッシュ時には多くのお客さんを運ぶ重要な路線です。
それじゃ、またの。
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!