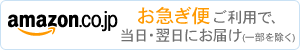- 京阪の乗り換え駅
- 特急停車駅
近鉄京都線では京都駅に次ぐくらい重要な駅なのに2面2線。

と思ったので、丹波橋にはどんな歴史、経緯があったのか調べてみました。
ざっくりと分かりやすくご紹介します。
近鉄丹波橋駅が小さな駅になった理由

- 元々、ひと様が住んでるエリア
- そもそも京阪と乗り入れする予定だった
- 乗り入れ解消になってしまう
- 利用者が段々増える
- 特急停めよう
とまぁ、こんな感じ。
京都市伏見区の中心地
伏見といったら何百年も前から人が行き交ってた場所なんで、駅を作るには土地を買わないといけません。
そんな所に巨大駅を作る事は難しいので、必要最低限の大きさにしたんだと思います。
多分、坂本竜馬とか新選組とかよく知ってる人は、伏見がどんな所かは知ってるはず
最初から京阪と乗り入れする予定
京阪乗り入れ構想は元々あったらしく、桃山御陵前~丹波橋くらいで乗り入れができるように鉄道計画を作ってました。
なので、近鉄側を無駄に大きくする必要はなかったんですよね。
京阪側は既に駅を完成させたんで。
まぁ実現するまでは17年かかってるんですけど。
京阪と仲違いする


と、近鉄と京阪の事業拡大のタイミングがズレてしまい、乗り入れは23年後の1968年に解消。
接続してた線路が無くなります。
利用人口の増加
利用者は増えるし、京阪との乗り換えができるっていう点。
伏見区は全国で見ても結構人口の多いエリアになってしまい、ダイヤ改正をせざるを得なくなってしまいます。
1998年には、当時あった京都線の快速急行の停車駅となりました。
まぁこの快速急行は2003年に廃止されるんですけど。
丹波橋駅が特急停車駅となる
2002年のダイヤ改正で特急停車駅になります。
それ以前から伊勢への観光客は増えてきてたらしく、お客さんの取り込みも狙っての特急停車駅への昇格なんだと思います。
だけど、周辺は住宅街。
簡単に駅を拡大する事はできないので、2面2線のまま丹波橋駅が特急停車駅となったワケです。
近鉄丹波橋駅あたりの航空写真を見てみよう

これは現在の航空写真です。
以下、同引用元:国土地理院地図
1961年~1969年の時の航空写真

まずは南側
左が京阪で右が近鉄線です。接続している線路が1本見えますね。

そして北側
今はただ単にオーバークロスしてますが、ちゃんと接続線路がついてます。
当時の配線図

引用元:丹波橋駅Wikipedia
配線図で見ると分かりやすいように近く描かれてますけど、実際にはちょっと駅から離れてます。
で、乗り入れそのものは良かったんですけど、全て京阪の丹波橋駅に移動したもんだから、主導権が京阪になったんですよね。
だから、近鉄車両は待たされることに。


そういう事もあって、近鉄と京阪の乗り入れが解消されてしまったのかも知れません。
決定的だったのは電圧アップ問題でしょう。
今でも残る、乗り入れの名残
現在でも乗り入れをやっていた時の名残があります。
まずは桃山御陵前駅に近い所。

京阪方向に向かって、空白地帯があります。

元々はココに線路がありましたが、今は駐輪場になってます。
土地の有効活用ですね。
この駐輪場は京阪が運営しています。
線路向こう側の、近鉄線との間は駐車場になってますね。
「丹波橋」駅名の由来
付近に「桑野丹波守」の屋敷があって、近くにかけられた橋が「丹波橋」だから。と言われてます。
なんし、地域名が「丹波」なんですよねこの辺。
そこを守る桑野さんの屋敷があったかどうか知りませんけど。
ちなみに、近鉄駅は元々「堀内駅」となってましたが、この駅名の由来は分かりませんでした。
桃山御陵前と近い丹波橋駅
もっと近い、大和八木~八木西口は色々な都合で同じ駅の扱いなので公式には最短ではないようです。
よくネタにされてる伊勢市~宇治山田間は0.6km
ですが、この2駅の間はカーブがあるので互いに駅をホーム上で確認する事はできません。
どっちかの駅が後から出来た、という事はなくて、どっちもほぼ同時期に開業しています。
よっぽど伏見の辺りは人が住んでたんでしょうね。
関連記事:近鉄の駅間距離を調べてみた
まとめ:近鉄丹波橋駅は降格と昇格を経験した
京阪との乗り入れ時には、駅として機能してなかったんですけどね。
乗り入れ解消で駅として戻り、最終的には特急停車駅にまで昇格した、色々とあった駅だったようです。
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!