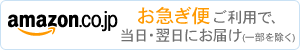近鉄大阪線はよく利用するんですが、時刻表を細かくは見てなかったので

と通るたんびに思ってたので、調べてみました・・・結構使ってますね。
今回は気になってた河内国分駅のことを好き勝手に調べて、まとめてみました。
河内国分駅の引き上げ線はかなり使ってた

引用元:Google Map
国分駅の引き上げ線は、ちょっと気になってました。
弥刀駅については以前に取り上げて解決済です。
>>弥刀駅、謎の引き上げ線。やる気のない構内踏切を探ってみた
想像を超える使用頻度

と思ってました。なんし鶴橋あたりの時刻表はちょくちょく見るので、「国分止まり」の普通があるのは把握してました。
でも、どんだけ出ているのかまでは見てなくて
平日ダイヤで国分始発が17本出ているとは思いませんでした。
土休日ダイヤは8本くらいです。(間違ってたらゴメンね)
通勤・通学需要のため

平日ダイヤと土休日ダイヤの本数に倍の差がありました。
この事から、通勤や通学のためだと考えられますね。
朝はあまり多くありませんが、特に夕方以降が多いです。
夕方からの電車の動きを時刻表で追ってみると
- 16時35分着の普通・河内国分行きが始まり
- 18時~19時がピーク
- 国分始発20時42分まで
というわけで、上本町→河内国分→上本町と行き来していることが分かります。
簡単な話、帰宅ラッシュ対応ですね。
国分から普通が出るのは、電車の後処理。
回送で走らせるのがもったいないから、営業させているのでしょう。
あまり多くはありませんが、柏原市→八尾市の需要に対応してます。
人の動き
柏原市にやってくるのは八尾市の人が多い
というわけで、夕方は河内国分まで行く普通も増やして動かしている、というわけです。
そのままだと優等種別にギュウギュウ詰めですからね。
河内国分駅の歴史

引用:Google Map/nasiji1026さん
河内国分駅は、近鉄大阪線(当時は八木線)の延伸時に同時開業しました。
隣の大阪教育大前のような追加駅ではなく、最初からありました。
関連記事:【近鉄の新駅シリーズ】大阪教育大前駅の新設はお金がかかった・・・
最初は2面2線の駅だった
1927年7月1日に開業しました。
すでに八木西口~大和高田は完成しているので、この時点で大阪線は八木まで完成です。
当時はまだ大和八木駅がなくて、今の八木西口駅に入ってました。
1929年1月5日に大和八木駅が完成し、桜井まで延伸します。
1938年6月に、河内国分に上下の待避線が設置。引き上げ線はまだありません。
当時の待避設備の状況
高安駅については情報なし。五位堂駅の待避線は1963年に設置されてます。
ですので、河内国分に待避設備ができるまでは
高安の次が大和八木
だったと思います。
1938年6月中には桑名~名古屋が開業し、ほぼ名阪のルートは完成してます。
将来のことも考えて河内国分に待避設備を作ったんでしょう。
追突事故

1966年11月12日、河内国分の駅構内で特急列車が準急列車に追突する事故が発生しました。
待避していた名張行き準急(1480系)に、宇治山田行き特急10000系・旧ビスタカーが衝突。
運転士が死亡し、43人が重軽傷を負った痛ましい事故がありました。
原因は、特急列車の運転士が信号を見落とした事だったようです。
引き上げ線の設置
1967年12月に引き上げ線が設置されました。
この辺りの日本経済はイケイケすぎて今では考えられないほど、景気が良かったのです。
人口が増えて、通勤通学の輸送力が求められるようになり、近鉄は輸送力増強のために投資を始めました。
そのうちの1つが河内国分で折り返す設備です。
河内国分駅に付けられた副駅名
河内国分駅には副駅名「関西福祉科学大学前」が付けられてます。
2011年12月26日に付きました。
駅からの距離は約1.2kmで、副駅名が付いている駅では・・・・どれくらい遠いんでしょうね。
また調べておきます。
河内国分駅の「国分」とは何じゃいな

引用:Google Map/上崎哉さん
国分はそもそも地名で、元は「国分寺」だと考えられます。
なぜかというと、寺が無くなったからです。
聖武天皇の勅命
741年、聖武天皇はこう言いました。

当時は災害や病気がメチャクチャ多くて、今とは違って宗教の力を借りるしかありませんでした。
そして作らせたのが「国分寺」です。
日本神道の事実上のトップである天皇が、なんで寺?と思うでしょうが、聖武天皇は仏教の力も借りるくらい切羽詰まってたのです。
なんせ神道は拝む対象が見えませんからね。
なぜ「国分寺」という名称にしたのかは不明。「分ける」って字はあまり良い印象がないのですがね・・・
国分寺を置く場所の条件として
- 人里から離れていること
- 交通の便は良いこと
- 役所に近いこと
他にもありますが、これらが条件でした。
参考:河内国分寺

引用:Google Map
大和川・国道25号線からは少し離れて、少し高めの土地にありました。
国道25号線は古い道の1つで、大阪と奈良を結ぶ道路でした。
もちろん昔はトンネルを掘る技術が無いため、柏原市を通るルートは阪奈ルートの重要な道路の1つです。
国分寺由来の駅は東京にも
河内国分駅も国分寺が由来ですが、東京のJR中央線にも「国分寺駅」や「西国分寺駅」があります。
あっちは、そのまんま使っているので読みが「こくぶんじ」ですが
河内国分駅は「こくぶ」となってます。
地名が元々「こくぶ」読みだったのが理由でしょう。
リズムも良いですしね。
柏原市の中心駅はどこやねん?

引用:Google Map/nasiji1026さん
柏原市の中心駅はJR大和路線の柏原駅とも言われてるし、河内国分駅とも。
でも市役所は大阪線・安堂駅が最寄です。
なんし、柏原市は柏原駅周辺と河内国分駅周辺の町が合併してできた市なので・・・どっちも中心駅と言えます。
ちなみに利用者数は河内国分駅の方が多いです。
特定日と平均を比べると話は違ってしまいますが、河内国分の方が多め。
大阪環状線の駅までの時間は
と、ほぼ差はなし。
通勤ラッシュ時間帯(平日7時台上り)の本数は
このように倍違います。
利便性の事も考えたら河内国分駅の方が中心駅に相応しいスペックでしょう。
まとめ:河内国分周辺は歴史があった

引用:Google Map
柏原市そのものの歴史が古く、3万年ほど前の遺跡が発見されてました。
また大阪と奈良を繋ぐ、交通の要所として古くから栄えている街です。
そういった理由から大阪線の延伸開業と共に駅も開業。
待避線の設置→引き上げ線の設置→急行停車駅
と、進化していきました。
さすがにこれ以上のレベルアップはないと思います。
今回はここまで。それでは、またの。
SNSに撮った写真を載せてるので、ぜひご覧ください。
スマホ画面用・写真ダウンロードページ
撮った写真をスマホの画面用サイズに切り取りました。ぜひ、お使いください。
Instagram
↑毎日20時頃に更新!主に近鉄車両を撮ってます。
Twitter
アカウントを持ってる方はぜひフォローを。
ファンティア
特によく撮れた写真をアップします。アップ済みから未公開まで
PIXTA
未公開写真を公開、販売中!